超高齢社会の到来に伴い、さまざまな疾病を起因として発生する障害はさらに複雑化するとともに、ロコモティブシンドローム、サルコペニアへの対応など、リハビリテーション医学・医療の果たすべき役割はますます大きくなっています。 現在当院でのリハビリテーション対象疾患の割合は脳卒中が6割と最も多く、ついで大腿骨頚部骨折をはじめとする整形外科疾患、パーキンソン病などの神経変性疾患、COPDなどの呼吸器疾患と続いていており、リハビリテーション科では更なる患者状態の改善、安全で効果の高いリハビリテーション医療を提供することを目標としています。 当院は脳血管疾患等Ⅰ、運動器Ⅰ、呼吸器Ⅰ、心大血管Ⅰなどの施設基準のもと、脳卒中ケアユニットに入院中の方、一般床に入院中で運動や練習の必要性が高い方々には365日リハビリテーションを提供しています。2018年度より悪性腫瘍に対するリハビリテーションにも力を入れており、がんリハビリテーションチームの立ち上げとともにがん患者リハビリテーションの施設基準も取得し診療にあたっています。また当院では地域包括ケア病棟が設定されており、急性期治療を経過し、病状が安定した患者さんに対して在宅や介護施設への復帰支援に向けた医療や支援も行っています。 発症または受傷後間もない方々に対して、できるだけ早期にリハビリテーションを開始し、不要な安静による機能低下を予防し、身体的な運動療法、身の回り動作の練習、神経心理学的な評価、嚥下やコミュニケーション能力の評価・練習を行いながら、基本的な生活活動の能力向上を図り生活の改善につなげたいと考えています。 リハビリテーション科では患者さんの状態改善のため更なる治療を進めてまいります。 リハビリテーション科部長 岩本 康之介(脳神経内科)

理学療法では医師の指示のもと、すみやかにお体の状態に合わせて介入します。患者さんの「早く良くなりたい」という要望に沿えるよう日常生活動作の練習を始めます。ベッドから起きあがる、座る、立ち上がる、歩くといった基本動作を担当の理学療法士とともに練習を重ねていきます。身体機能、体力の向上に合わせて、実践的な屋外歩行練習も行います。また、必要に応じてご家族に動作介助の方法をお伝えし、家屋改修のアドバイスを行っています。

作業療法では脳卒中や整形疾患、内科的疾患等により日常生活活動に支障が生じた方々に対して練習を行います。入院早期から運動機能や高次脳機能の改善を図りながら代償的手段も取り入れ、食事や移乗、トイレなどの基本的な生活動作の早期獲得を目指しています。またその方の役割に合わせて家事や書字、パソコン操作などの練習も行っています。退院前には多職種と連携しながら必要に応じてご自宅を訪問し、住環境の評価や福祉用具の提案にも関わっています。

言語聴覚療法では脳卒中後の構音障害、失語症、高次脳機能障害、摂食嚥下障害の方に対して評価と練習を行います。嚥下機能評価では患者さんの状態に合わせて、神経内科医と嚥下造影検査や嚥下内視鏡検査を実施し、その方に適した食環境の調整を行っています。また、認知症疾患医療センターにおける「もの忘れ外来」では高次脳機能評価を担当し、医師、看護師、ソーシャルワーカー等と連携しながら認知症の方が住み慣れた地域で生活を続けていく為の診療に携わっています。
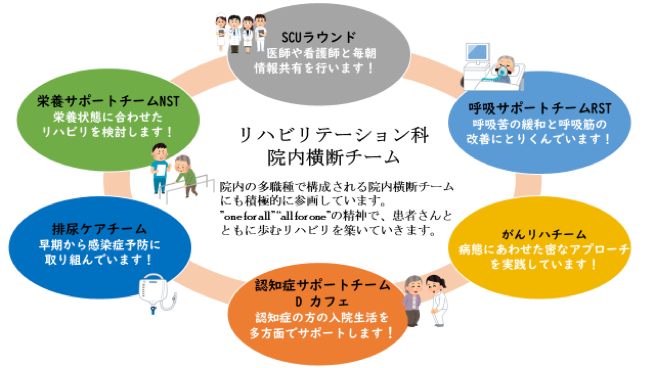
リハビリテーション科の新人教育の目標は、担当する患者さんに対して適切な分析と介入を行うための臨床思考過程を身に着けることです。新人職員には1年間スーパーバイザーがつき、サービスの質的向上を図るべく臨床業務を指導する体制を整えています。また、指導に偏りが生じないように、指導経験者がアドバイザーとして教育の進捗状況を把握し、スーパーバイザーに適宜助言を行う指導体制をとっています。指導に当たってスーパーバイザーは育成的視点に立ち、クリニカル・クラークシップ方式で新人職員の成長度合いに応じた指導を行っています。また、職員1人1人が院内外での勉強会や研修会を通して研鑽を積むとともに、学会発表や地域での講演活動等を行っています。
装具は、脳卒中後のリハビリに欠かせない重要な器具であり、脳卒中治療のガイドラインでもその効果が科学的に認められ、装具を使用することが強く推奨されています。
当院リハビリテーション科では、患者様の歩行機能の改善を目指し、「ゲイトイノベーション」「ゲイトソリューションデザイン」という装具を活用しています。
【装具の特徴】
① 自然な歩行の実現
油圧の力を利用して足首の動きをサポートすることで、自然に近い歩行が実現できるようになりました。
② 患者様に合わせた調整が可能
「ゲイトイノベーション」は、太腿の周径や高さの調整が簡単にできるため 患者様一人ひとりの身体状況に合わせた歩行サポートが可能です。
③ 研究で効果が証明
これらの装具は研究でも効果が証明されており、筋活動の増加や歩行速度の改善が期待できると報告されています。
当院では、脳卒中発症早期から適切な装具を用いたリハビリを行うことは、その後の機能回復を大きく左右すると考えています。そのため、「ゲイトイノベーション」「ゲイトソリューションデザイン」を活用し、患者様が一日でも早く機能回復や社会復帰ができるように努めています。
今後もこのような取り組みを継続し、スタッフ一人ひとりが日々の臨床を通じて専門性を高めるとともに、研究や自己研鑽を重ね、より質の高いリハビリテーションを提供できるよう取り組んでまいります。
【画像】(左:ゲイトイノベーション 右:ゲイトソリューションデザイン)


| 村田和人 | 繰り返す過食の障害メカニズムについての考察ーもの忘れ外来受診2症例からの検討、第25回言語聴覚学会 |
| 村田和人 | 初期症状に色覚異常が疑われたマルキアファーヴァ・ビニャミ病の一例、第45回日本高次脳機能学会 |
| 齋藤 隆之 | 生成AIは言語聴覚士の夢をみるか?、第25回日本言語聴覚学会 |
| 齋藤 隆之 | 高齢者の摂食嚥下の問題点と対応、第15回日本腎臓リハビリテーション学会 |
| 柳川 大貴 | 足関節骨折後のWBLTと降段動作時の足関節背屈角度の関係性、日本運動器理学療法学会 |
| 石川 大輔 | 左USNにより受動的注意が低下した症例に対しレーザーポインターを実施した一症例、日本神経理学療法学会 |
| 石川 大輔 | 右中等度片麻痺を呈し連合反応・連合運動を認めた左放線冠梗塞に対する理学療法経験、共済医学会 |
| 金城 雅秀 | 身体図式の再構築により日常生活動作の介助量軽減に至った症例に対する一考察、共済医学会 |
| 山口 雅弘、村田 和人、北村 真理子、稲垣 絵里 | 目黒区地域ケア個別会議検討役員、目黒区地域ケア個別会議 |
| 鴻真一郎 | 老人保健健康増進事業「訪問による認知症リハビリテーションの効果についての調査研究事業」データ収集、日本作業療法士協会 |
| 鴻真一郎 | 認知症OT評価デルファイ調査員、日本作業療法士協会 |
| 鴻真一郎 | 認知症実践プロトコール研修アドバンスコースファシリテーター、日本作業療法士協会 |
| 鴻真一郎 | 日本作業療法学会 演題査読員、日本作業療法士協会 |
| 田村 龍太郎 | 目黒区介護予防リーダー養成講座 講師、目黒区介護予防事業 |
| 田村 龍太郎 | 目黒区介護予防体操 医療監修、目黒区介護予防事業 |
| 田村 龍太郎 | 東京都理学療法学術大会 教育・地域振興局 局長、東京都理学療法学術大会 |
| 柳川 大貴 | 第43回 東京都理学療法学術大会 演題査読員、東京都理学療法学術大会 |
| 柳川 大貴 | 臨床実習直前評価 講師、専門学校 社会医学技術学院 |
| 土橋 夏実、石川 大輔 | スポーツ学習・推進部派遣職員、子どもの健康安全部派遣職員、東京都理学療法士会 |
学会、地域貢献(2023年度分)は、以下のリンク参照
| 日本理学療法士協会 | 運動器 認定理学療法士 |
|---|---|
| 呼吸器 認定理学療法士 | |
| 臨床実習指導者講習修了資格 | |
| 3学会合同呼吸療法認定士認定委員会 | 3学会合同呼吸療法認定士 |
| 日本臨床栄養代謝学会 | NST専門療法士 |
| 日本作業療法士学会 | 臨床実習指導者実践研修修了資格 |
| 日本言語聴覚協会 | 失語・高次脳機能障害領域 認定言語聴覚士 |
| 摂食嚥下領域 認定言語聴覚士 | |
| 日本摂食嚥下リハビリテーション学会 | 日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士 |
| 日本神経心理学会 日本高次脳機能障害学会 |
臨床神経心理士 |
| 役職 | 脳神経内科医長・リハビリテーション科部長 |
|---|---|
| 資 格 (専門医等) | 日本神経学会専門医・指導医、日本脳卒中学会専門医、 内科学会認定医・総合内科専門医 |